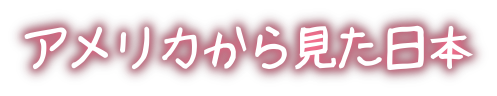パラオの国旗は黄金に輝く満月が青空を背景に浮かぶものだ。
パラオの人々にとって、満月は地球の周期的活動の頂点であると同時に祝い事に最適な時を表す。
その満月がパラオ人の結束と運命を象徴し、青い背景は長きに渡った外国の権威が彼らの土地から去ったことを象徴しているという。
この国旗はアルモノグイの第二伝統首長であるブラウ・スケボン氏がデザインしたもので1980年に多くの候補の中から選ばれたものだ。
ベラウ国立博物館のインタビューに答えるスケボン氏は旗に込められた思いを次のように語っている。
「パラオには満月の日は一ヶ月の中で最も縁起のよい日だとする言い伝えがあります。つまり満月の日は物事を始めるのに最適な日なのです。また旗の色にも意味があります。青い背景は太平洋を表すと共に、私たちを植民地統治した国々、スペイン、ドイツ、日本、アメリカの影を表しています。
そして黄色は健康と反映を表しています。ですからこの旗は、私たちはかつて植民地支配下にあったけれど、今は繁栄し強くなって独立するんだということを表しています。また、満月を少し左寄りにしたのは、旗が風にはためいたとき、ちょうど満月が中央に見えるように工夫したものです。」
このエピソードの他には、親日的なパラオの人々が「日本とパラオは兄弟である」という強い思いを持っており、日本が太陽であれば、我々は月だと解釈する人も数多くいるからだというものもある。また月が少し左寄りになっているのも、デザイン上の工夫だけではなく、日の丸が真ん中にあることから、同じにするには忍びないということで少しずらしているというエピソードもある。
いずれにせよ、国旗がとてもよく似ている日本とパラオ両国は切っても切れない運命を共有した絆の深い国であった。
戦後の教育でこの両国の歴史が全く教えられなくなったのはとても残念だ。
前回にこの島での凄まじい死闘の様子は書いた。
今回はその死闘が始まる直前のエピソードをご紹介したい。
私はこの話を何回も読んだことがあるのだが、それでも毎度毎度、涙なくして読めない。
本当に日本男児の潔さと勇気と人情が詰まるに詰まった話だと思う。
どうぞ一人でゆっくりと静かに読んでみて欲しい。
(電車の中だと泣いてしまうかもしれないから要注意!)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
当時、ペリリュー島には、899名の島民がおり、島民たちは皆、白人統治の過酷な時代を知ってる。
日本兵とはすっかり仲良くなっており、日本の歌をいつも一緒に歌っていた島民たちは、集会を開いた。
そして全会一致で彼らは、大人も子供も一緒になって日本軍とともにアメリカ軍と「戦おう」と決心した。
パラオの村民の会議は、古来からの習慣で村人全員が参加し、話し合いは全員がひとり残らず納得するまで、何日でも続けて行われる。
つまり全員が日本軍と共にアメリカ軍と戦うことを決心したことを示している。
全員一致で「日本軍とともに戦う」と決めた彼らは、代表数人で日本軍の守備隊長のもとに向かった。
当時のペリュリューの守備隊長は、中川州男(なかがわくにお)陸軍中将(任期当時は大佐)。
この中川大佐がペリリュー島に赴任したのは1943年。
日本を出国の際、奥さんに「今度はどちらの任地に行かれるのですか?」と聞かれた中川中将は、にっこり笑って「永劫演習さ」とだけ答えられた。
「永劫演習」というのは、生きて帰還が望めない戦場という意味だ。
そういう中川隊長なら、パラオの島民たちが、自分たちの頼み「一緒に戦うこと」をきっと喜んで受け入れてくれるに違いない。ただでさえ、日本の兵隊さんたちは兵力が足りないのだから。
ペリュリューの村人たちは、そう思い、中川中将のもとを訪ねた。そして中川中将に
と強く申しでた。
「村人全員が集まって、決めたんです。これは村人たち全員の総意です。」と。
中川隊長は、真剣に訴える彼らひとりひとりの眼を、じっと見つめながら黙って聞いておられた。
一同の話が終わり、場に沈黙が。。。
すると、突然その沈黙を切り裂くように中川隊長は、驚くような大声をあげた。
村の代表たちは、一瞬、何を言われたか理解できなかった。
耳を疑った。
そのときは、ただ茫然とした。
指揮所を出てからの帰り道、彼らは泣いた。断られたからではなく、中川隊長に土人と呼ばれたことがショックだったからだ。
それは怒りからではなかった。 あんなに仲良くしていたと思っていたのに、兄弟のように親しみをもって毎日を過ごしていたと思っていたのに、
という悲しみの方が大きかった。
日頃から、日本人は、自分たちのことを仲間だと言ってくれていたのに。同じ人間だ、同じ人だ、俺たちは対等だと言ってくれていたのに。 それが「土人?」
信じていたのに。。。あれはみせかけだったのか?
集会所で待っている村人たちに報告した。
みんな「日本人に裏切られた」という思いで、ただただ悲しくて、悔しくてみんな泣いていた。
何日かが経った。
いよいよ日本軍が用意した船で、パラオ本島に向かって島を去る日がやってきた。
港には、日本兵はひとりも見送りに来ない。島民たちは、一人一人、船に乗り込んでゆく。
島を去ることも悲しかったけれど、それ以上に、仲間と思っていた日本人に裏切られたという思いが、ただただ悲しかった。
汽笛が鳴った。船がゆっくりと、岸辺を離れはじめた、その瞬間!
島から
「おおおおおおおおおおおーーーつ!!」
という雄たけびがあがった。
島に残る日本兵全員が、ジャングルの中から、浜に走り出てきたのだ。
そして一緒に歌った日本の歌(「海ゆかば」)を歌いながら、ちぎれるほどに手を振って彼らを見送ってくれたのだ。
その時、船上にあった島民たちには、はっと気付いた。
日本の軍人さん達は、我々村人を戦火に巻き込んではいけないと配慮したのだと。
そのために、心を鬼にして、あえて「土人」という言葉を使って我々を冷たくはねのけたのだと。
そうしないと我々が絶対に引かない、戦うと言い張るということを見越して。。
船の上にいる島民の全員の目から、涙があふれた。
そして、岸辺に見える日本兵に向かって、島の人たちは涙でかすむ目を必死にあけて、ちぎれるほど手を振った。
船の上から、ひとりひとりの日に焼けた日本人の兵隊さんたちの姿が見えた。みな、笑っている。歌声が聞こえてきた。そこには中川隊長の姿もあった。他のみんなと一緒に笑いながら、手を振ってくれていた。とても素敵な笑顔だったそうだ。
日本軍の戦死者10,695名・捕虜202名
米軍の戦死者2,336名・戦傷者8,450名
島民の死者・負傷者0名
この数字を見るだけでも、私は胸がつまる。日本人の「自分達の戦いに島民を巻き込まない」という決死の覚悟と思いがそこに詰まっているようで。
ペリリュー島には「ペリリュー神社」が建立されているが、そこにある石碑にはある人の言葉が刻まれている。
諸国から訪れる旅人たちよこの島を守るために日本軍人がいかに勇敢な愛国心をもって戦い そして玉砕したかを伝えられよ。
米太平洋艦隊司令長官 C.W. ニミッツ
敵ながらあっぱれ!の戦いをしたという賞賛の思いを敵国であったアメリカ人の司令官が言葉で残している。
最後に戦後にパラオ人によって作られたパラオ独立記念の歌を紹介して終わろうと思う。
一 激しく弾雨(たま)が降り注ぎ
オレンジ浜を血で染めた
つわものたちはみな散って
ペ島はすべて墓(はか)となる
(注:ペ島=ペリュリュー島のこと)二 小さな異国のこの島を
死んでも守ると誓いつつ
山なす敵を迎え撃ち
弾射ち尽くし食糧もない三 兵士は桜を叫びつつ
これが最期の伝えごと
父母よ祖国よ妻や子よ
別れの”桜“に意味深し四 日本の”桜“は春いちど
見事に咲いて明日は散る
ペ島の”桜“は散り散りに
玉砕れども勲功はとこしえに五 今もののふの姿なく
残りし洞窟の夢の跡
古いペ島の習慣で
我等勇士の霊魂守る六 平和と自由の尊さを
身をこなにしてこの島に
教えて散りし“桜花“
今では平和が甦る
七 どうぞ再びペリリューヘ
時なしさくらの花びらは
椰子の木陰で待ちわびし
あつい涙がこみあげる